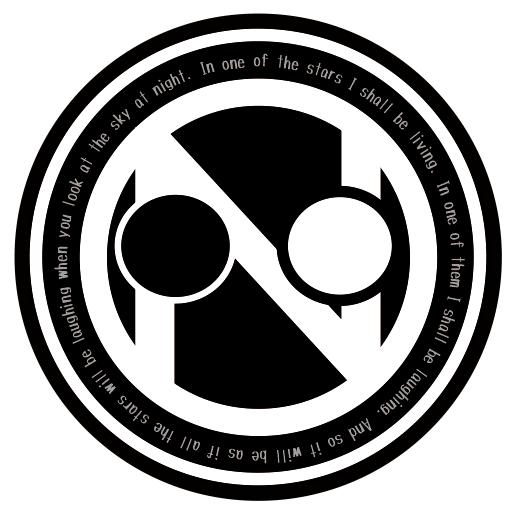松村克弥監督制作のカルト映画「オールナイトロング」をご存知だろうか。1992年に制作されたR15指定の映画だ。全編に血しぶきが溢れる残酷表現を貫いた異色作で、悪名高い「ギニーピッグ(1985)」を連想させる作風が映画公開当時話題となった。
君は松村克弥の「オールナイトロング」を知っているか。

今回レビューする第一作目は2014年現在においても、ビデオソフトのみでDVD化されていない。ビデオパッケージには「映倫が審査を拒否した問題作」とのキャッチコピーが書かれているが、一方で世間のゲテモノ的評判とは裏腹に、映画自体はシンプルな構成となっているのは面白い。
当初、映倫の審査員全員は成人指定にしようとしたものの、松村克弥監督と大揉めしたと言うが、宮崎勤による東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の影響から、この手の過激なスプラッター作品へのバッシングが強まったからだとされている。その代表的作品が「ギニーピッグ」シリーズなのだが、この様な何のメッセージ性も無く特撮技術を無駄遣いしただけの悪趣味な作品と一緒にされては松村克弥監督も激怒するというものだろう。
あらすじ
定時制の工業高校に通い、航空整備士を夢見る慎治、超エリートの進学校に通い、一流大学を目指す徹也。裕福な上流階級に生まれ、自由な日々を送る健介の3人は、残忍な通り魔殺人事件に巻き込まれたことによって知り合う。彼らは軽い気持ちで、次の火曜日にそれぞれガールフレンド同伴で、健介の家でホームパーティを開くことを約束した。知り合いの女の子に片っ端から電話をかけてはふられる健介は、ある日、夢に出てきた女にそっくりの良子という女性に出会う。大人の匂いのする彼女に憧れる健介だったが、良子は彼を弄び、彼の夢とプライドはズタズタに引き裂かれてしまう。予備校で一目惚れした江理をパーティに誘うことを考える徹也は、プレイボーイの玉利に協力を頼むが、玉利は彼の純情を無残にも裏切ってしまう。通学途中で見かけた女子高生の葉子と知り合った慎治はお互いにひかれあい、楽しい日々を送るが、パーティの当日不良グループに襲われ、葉子はレイプされ取り返しのつかない重傷を負わされてしまう。身も心もボロボロの3人は、健介の父親の散弾銃を取り出し、不良グループのアジトに乗り込んだ。おどすつもりだけだったはずの散弾銃の発砲で、アジトは狂気と殺戮の場と化し、入り乱れての殺し合いになる。そうしてただひとり生き残った徹也は、玉利も殺し、雨の街を不気味な笑みを浮かべて歩くのだった。
KINENOTEより
さて「オールナイトロング」は我々に何を提示したのだろうか。結論から言えば、この日本社会の構造を忌憚なく描いた「極めてシンプルな作品」というのが私の印象である。
では、日本社会の構造とな何であろうか。図らずとも、この作品の主題は冒頭の女子高生惨殺事件にすべてが集約されている。(余談だが、この女子高生を演じたのは現在声優として活躍する柚木涼香女史(角松かのり名義)である。柚木女史は続編のオールナイトロング2、オールナイトロング3 最終章にも出演している。)
松村克弥が提示した日本的狂気の世界
何の変哲も無い平時の朝、3人の少年―斎藤慎治、鈴木健介、田中徹也が、偶然踏み切りの前に居合わせ、突然、少女が通り魔にめった刺しにされるという現場に遭遇するのだが、この通り魔が一見するとごく普通のサラリーマンで普通の人にしか見えないのだが、その狂気の描写が素晴らしい。
「あのすいません、ちょっとお尋ねしたいのですが、この場所を教えてください」とサラリーマン風の男は懐から地図を取り出し、女子高生に尋ねるのだが、懐から取り出したものは地図ではなく、真っ白なハンカチなのだ。
女子高生は困惑するが、それでも男は真っ白なハンカチを見せつけ「ここです、ここなんですよ!」と叫び続ける。只ならぬものを感じた女子高生は顔を背けるが、すると男は突然激昂し、懐からナイフを取り出して女子高生を滅多刺しにするのである。
ただ呆気に取られるばかりである。そこに至るまでには何の伏線も何も無い、ただ唐突に現れた異常者によって、何の意味も無く女子高生は殺されたのである。
一見すると、実にシュールな光景だ。この唐突さには評価が分かれるところだが、私はこのシーンを観た時「これぞ偽りなき日本社会の姿そのものである」と妙な感動を覚えたのである。
「何を馬鹿な」と思うかも知れないが、2011年の角田美代子の事件を思い出してほしい。あるいは、埼玉幼女連続誘拐殺人事件(1988-1989)の宮崎勤でも、秋葉原通り魔事件(2008)の加藤智大でも何でも良い。この国で現実に起きた事件の数々を思い出してほしい。
無論「通り魔」というのは人の出入りが自由な場所における突発的なもので予測不可能な事件というのは各国共通であろうが、日本における「通り魔による犯行」というのは柳田國男以前から語り継がれる伝統的なカタチなのだ。
近年は「無敵の人」というカタチで毎年のごとくニュースを賑わせている。
近年話題の「ゲーテッド・コミュニティ」などは、そうした住み分けが極端なカタチで現れたものと見ることも出来る。日本では現在のところ、マンション単位での「ゲーテッド化」が広まりつつあるが、基本的にこの国では社会階層による住み分けは(東京・大阪などの一部の大都市圏を除いて)行われていないのが普通だ。
金持ちも貧乏人も、宗教家も半グレも、あらゆる階層が渾然一体となっている。そこには何の「境界」も存在しない、「常人」と「狂人」も何の住み分けもなされていない世界。
奇しくも、近年はそうした「境界」の無さを証明した年であると言えるのではないか。
この国には正気と狂気の間に境界は存在しないのである。
我々は、この「正気と狂気」が渾然一体の土台の上で社会生活を営み、仮初の安全大国日本という幻想、つまり「アンゼン」のもとに生きているのだろう。そして「アンゼン」の対価とは、劇中冒頭の女子高生の如く「狂人による理不尽な悪意」による心身への被害によって支払われるのだろう。
そして、正気と狂気の境界の希薄さは、それが故に「常人」を「狂人」へと転化し得る状況を容易に生み出す。
劇中、アジトに殴り込んだ三人が猟銃で不良の一人を射殺した瞬間、三人の狂気が爆発し、復讐が見境なき殺し合いへと発展したが、それは単なる結果に過ぎない。この国の「日常を侵食する狂気」に彼等自身が取り込まれただけなのだろう。
ネタバレになるが、主人公の一人である斎藤慎治の彼女をレイプした連中は不良達ではなかったと言う。つまり、この惨劇もまた第三者の「狂気」が招いた結果なのだ。
惨劇の後、最も気弱だった優等生の田中徹也は、一人生き残った不良少女を車で轢き殺し、自分に好意的だったジゴロの玉利をも惨殺する。
そして劇中ラスト、田中は視聴者へ不気味な笑顔を見せ付け、何食わぬ顔で「日常」へと帰還する。田中のその後が描かれる事は無いが、恐らく常人の皮を被った狂人として生きていくのだろうか。
否、この国には「常人」と「狂人」の境目など、最初から存在しないのかもしれない。日本社会を生きるとは、正気と狂気の境界無き世界を否応なしに歩んでいく事なのだろうか。